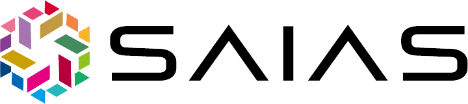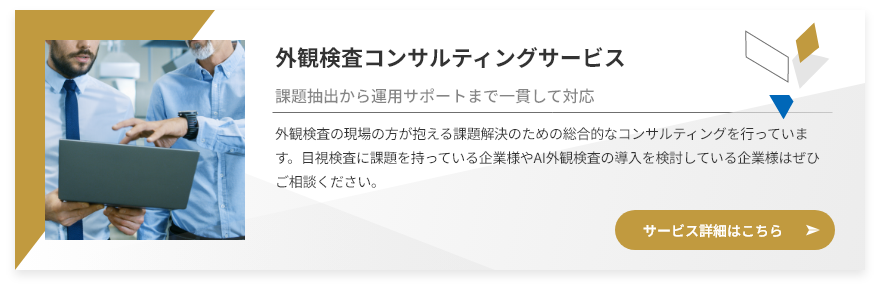外観検査におけるキズの基準とは?
JIS規格との関連性や設定方法を解説

外観検査とは、製品表面にキズや汚れなどの異常がないかを目視や機械で確認する品質管理の重要工程であり、多くの製造現場で欠かせない役割を担っています。
しかし、実際の現場では「どの程度のキズを不良とするか」といった判断にばらつきが生じやすく、明確な基準がなければ検査品質を一定に保つことは困難です。こうした課題を解決するため、JIS規格に基づいた基準設定や、AIを活用した外観検査の自動化が進められています。
本記事では、外観検査の基本からJIS規格との関係性、基準設定の手法までをわかりやすく解説します。
目次
外観検査とは
外観検査とは、製品の表面にキズや汚れ、へこみ、変形、色ムラといった外観上の欠陥がないかを目視や検査機器を用いて確認する工程です。こうした異常は、たとえ製品の機能に直接影響を及ぼさない軽微なものであっても、顧客の印象やブランドの信頼性に大きく関わるため、品質管理において重要視されています。
外観検査は自動車部品や電子機器、金属加工品、化粧品容器など、あらゆる製造業で導入されています。
外観検査で基準設定が求められる背景

外観検査は一見するとシンプルな工程に思えますが、実際にはキズひとつ取っても形状や大きさ、深さなどさまざまなパターンがあり、同じキズでも検査員によって合否の判断基準が分かれることも珍しくありません。
こうしたばらつきの主な原因は、検査基準が曖昧であったり、数値化されていなかったりする点にあります。このような問題を防ぐためには、「どの状態を不良とするか」「合否をどう判断するか」といった明確な基準を設定することが重要です。特にクレーム対応や品質保証の観点からは、誰が検査しても同じ結果が得られるよう、客観性と再現性を備えた検査基準の設定が欠かせません。
外観検査の基準設定のメリット
外観検査において明確な基準を設けることは、製造現場全体の品質管理レベルを向上させる重要な施策です。さらに、検査員の属人的な判断を排除し誰もが同じ基準で評価できるように体制を整備することで、検査作業の効率化と品質の安定化が図れます。
ここでは、外観検査の基準設定による主なメリットを3つ紹介します。
不良品削減による品質向上
最大のメリットとして挙げられるのが、製品の品質向上です。検査における明確な基準をサンプルや数値として定めておくことで、検査員の経験や主観に左右されず、一貫した合否判定が可能になります。その結果、キズの見逃しや過剰な判定が減少することで不良品の市場流出が減り、製品の品質が安定します。
人的コストの削減
従来の外観検査では、経験を積んだ検査員の確保や人材教育に多大なコストがかかっていました。しかし、検査基準が明確に定義されていれば、新人検査員でも一定の品質判断が可能になり、教育期間の短縮や検査工程の標準化が実現できます。また、検査基準をもとに機械による自動化システムを導入することで、省人化や業務効率化も期待できます。
顧客満足度の向上
統一された検査基準により製品品質が安定すれば、顧客の安心感にもつながります。特にBtoB取引においては「品質管理が徹底されている企業」として信頼を得やすくなり、継続的な取引や企業イメージの向上にも寄与します。
外観検査とJIS規格の関係性

外観検査の基準を設定する際に参考となるのが「JIS規格(日本産業規格)」です。JISには外観検査に関する方法や観察条件、合否の判断基準などが規定されており、製造現場や取引先と共通の認識を持つための指針として活用されています。
ここでは、基準設定のポイントと代表的なJIS規格の例について詳しく見ていきましょう。
検査方法の標準化
検査結果のばらつきを防ぐためには、「どのような方法で検査を行うか」「どのような環境下で観察するか」を統一することが重要です。検査方法・環境の標準化には、以下のJIS規格が参考になります。
| 代表的なJIS規格 |
|---|
|
例えば、ボルトやネジといった大量生産されるパーツをすべて検査する場合、多くの時間とコストを要するため現実的とは言えません。そこで「JIS Z 9002」に基づく抜取検査を採用することで、効率的な外観検査を実現できるようになります。
判定基準の明確化
外観検査では「どの程度のキズや変形を不良とするか」を明確に定める必要もあります。その際に参考となるのが、以下のJIS規格です。
| 代表的なJIS規格 |
|---|
|
例えば、パイプやシャフトといった円筒形製品の外観検査では、見た目の均一性だけでなく、手触りや光沢のムラも評価対象となります。こうした場合には「JIS B 0031」の定義に基づいた検査が有効です。
品質保証の基盤として活用できるJIS規格
JIS規格に準拠した外観検査基準を導入することで、製品品質を客観的に証明する手段となります。仮に企業間で品質トラブルが発生した際でも、JIS規格に準拠し明文化された基準があれば、原因の特定や責任の所在を明らかにできます。
また、JIS規格の多くはISO規格など国際標準との整合性が取れており、海外企業との取引においても信頼性の高い品質保証の基盤として活用できます。
JIS規格以外の基準設定方法

JIS規格は業界共通の指針として広く利用されていますが、製品の特性や業界によってはより厳しい個別の基準設定が求められる場合もあります。こうした状況で多くの企業が活用しているのが「見本(サンプル)」を用いた基準設定です。
ここでは、代表的な3つの見本による基準設定について解説します。
限度見本
限度見本とは、合否の判定基準を実物で示した見本です。「このキズは許容範囲」「これ以上は不良」といった判断基準を視覚的に共有できるため、検査員同士の認識のずれを防ぐために効果的です。実際の製品と限度見本を比べることで、判断のばらつきを抑えることができます。
不良見本
不良見本とはその名の通り、NGと判断される典型的な欠陥サンプルを集めた見本です。
「この状態は明確に不良である」という判断を誰もが理解しやすくなるため、検査ミスの防止に役立ちます。新人検査員の教育用資料としても効果的です。
標準見本
標準見本とは、理想的な製品状態を示す見本です。特に色や光沢など、数値化が難しい外観項目においては標準見本を活用することで基準が明確になり、検査精度が向上します。
AIを活用した外観検査の基準設定

近年、製造業では人手不足が深刻化しており、特に外観検査のように熟練の経験が求められる工程では、検査員の確保や育成が大きな課題となっています。こうした背景から、AIを活用した外観検査の導入が急速に進んでいます。
AIを用いることで、製品表面の微細なキズや異常を人の目に頼らず高精度かつ客観的に検出できるようになります。従来はベテラン検査員の経験や勘に依存していた合否判定も、AIが過去の検査データや画像を学習することで高精度の判定が可能になり、判断の客観性と一貫性が向上します。
例えば、AIに「このような形状や大きさのキズは不良」といったキズの基準を学習させれば、検査結果を定量的かつ自動で判定できるようになり、ヒューマンエラーや見逃しのリスクが大幅に低減します。
さらに、24時間稼働可能なAI検査システムを導入すれば、夜間や休日など人手が足りない時間帯にも安定した検査を継続でき、製造ライン全体の効率化・省人化に貢献できるでしょう。
このように、AIによる外観検査は人手不足への対応と品質の安定化を同時に実現するソリューションとして多くの現場で導入が進んでいます。
外観検査のシステム化や基準設定を行うために
外観検査は、製品の品質はもちろん、企業やブランドの信頼性、市場での競争力にも直結する重要な工程です。特に人手不足が深刻化している昨今では、限られた人員で検査品質を維持するには限界があり、基準設定による効率化やAI活用による省人化がカギを握っています。
しかしながら、社内でゼロから検査基準を整備したり、AIを活用した検査体制を構築・運用したりするには、多くの時間と専門的な知見が求められます。そのため、外観検査の標準化やAI検査の導入にあたっては、専門家の支援を受けることをおすすめします。
SAIASでは、製造現場が抱える課題を直接ヒアリングし、外観検査ラインの自動化や最適化、ライン拡張などに向けた提案を行っています。ご提案の際には必ず現地へ足を運び、実際の運用状況を確認しながら課題を抽出。導入後も継続的な改善提案やアフターフォローを通じて現場の変化に寄り添い続けます。
「外観検査の自動化やAI化に取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」
そんなお悩みをお持ちの企業様は、ぜひ一度、SAIASまでお気軽にご相談ください。